・企業、団体の組織力向上やリーダーの育成を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・スポーツの価値向上を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・メディア出演のご依頼
について、お気軽にこちらのフォームよりお問い合わせください。
追ってこちらからお返事させていただきます。


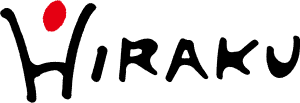
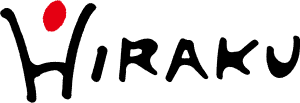


千葉ロッテマリーンズの吉井監督の「機嫌のいいチームを作る」という本を読みました。ひとりひとりの心理的安全性を作って、その人のポテンシャルを引き出しすることでよりよいチームを作る。自分が思っていることを伝えられることで責任感も生まれてくる。全ての情報も明らかにすることで、透明性のある組織を作っていく。そのことにより、 通常ではもっとストレスが溜まると考えられる人事に対しても理解を得やすくなる。
野球は、試合中において監督が指示をするケースが多いスポーツになる。一方で、ラグビーの場合は、どうしても選手が試合中に意思決定をする機会が多いので、主体的なチームになるのは当然の流れになる。野球においても主体性が大事というのは、自分自身としては、試合しかイメージできていなかったと反省しました。試合中のみならず、普段の練習から自分が自分の強みとか弱みとかをしっかり理解できて、その上でどんな練習をして、どんな振り返りをしてコーチとどんなやり取りをして自分を成長させていくのかと考えると、やはり主体性というのはとても大事になるということを改めて思いました。
枠の中で、自主的にやることを自主性と吉井監督は言っているのですが、そもそもこれで良いのか?という前提を疑ったり、そもそもの常識のようなものを疑い、ルールや仕組みそのものを変えていく気概や行動が主体性には大事になってくる。では、どうすれば主体的に動ける人が増えるのか、これらが大事なテーマになってきます、まずは、なぜ自分が主体的に動けるのか?それはたくさんの原体験から成り立っていると思いました。自分で考えて動えて動いてみて、得られるものに対する達成感がとてもワクワクしてきたので、そのことをどんどん進めていきたいと思えるようになった。最初は小さなことだったかもしれない。でも回数が増えて、質も高まる中で習得していった。そのように考えるとやはり場を作って、学んでいくことが本質だなと思いました。
キャプテン論も面白かったです。吉井監督曰く、キャプテンいらなくて、それぞれのリーダーシップでチームの色を染めていくチームにしたいと書かれている。キャプテンはそこまで必要ないというのも、面白い。1対1の局面が多いスポーツならではでもある。ラグビーは流動的でダイナミックで、最後の最後一人一人の判断だが、そこに至るまでに、みんなでどういうプレーするのか、相手がどうなっているか、みんなで話し合って方向性を決めていく。オフィシャルリーダーがいた方が、スムーズである。ユニット単位で、やることも多い、チームで専門的なスキルを融合させていかないといけない、擦り合わせていく中でも、リーダーがいる。もう少し考えると、ラグビーの場合、特に日本代表、本当に色々な背景を持った選手たちが来るので、その中でチームを作る時にも、リーダーがいることが大事になるとも思いました。
その他にも、意思決定の際に、データと直感のバランスが7対3にしている。直感の方もこれまでの体験値の積み重ねになる。なおかつ吉井さんは、感情をコントロールして判断しているので、とてもロジカルに考えられている印象を持ちました。偶然のコミュニケーションを創出するという言葉も面白かったですね。リーダー自身が動きながら、情報がどう入ってくるようにするのかを考えている。コーチから、トレーナーからの情報収集ルートを持つ。デジタル・様々な人の主観・自分の主観を織り交ぜて決断していく。その意思決定を最後は責任を取る。監督の仕事も大変だけど、楽しいだろうなと思いました。
最近、読書以外の時間を多く作っていたので、久々に読書をしましたが、自分自身としても・HiRAKU としても色々と考えるきっかけになりましたし、色々なプロジェクトについて改めて考えるきっかけになりました。スポーツ好きの方は読んでみると良いなと思いました。
・企業、団体の組織力向上やリーダーの育成を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・スポーツの価値向上を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・メディア出演のご依頼
について、お気軽にこちらのフォームよりお問い合わせください。
追ってこちらからお返事させていただきます。

