・企業、団体の組織力向上やリーダーの育成を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・スポーツの価値向上を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・メディア出演のご依頼
について、お気軽にこちらのフォームよりお問い合わせください。
追ってこちらからお返事させていただきます。


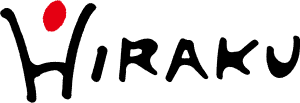
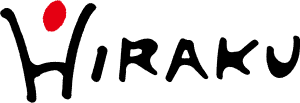


ケニアに続き、モンゴルへ。
7月のケニアに続き、8月にはモンゴルを訪問した。
きっかけは、大阪eスポーツの普及を目指す団体「OeGG」とのご縁で、モンゴルの首都ウランバートルで開催されたジャパンフェスティバルのトークセッションに登壇する機会をいただいたためだ。登壇自体は20分ほどだったが、eスポーツの広がりや大阪、万博の魅力について話をすることができた。 モンゴルといえば、私にとっては、「モンゴル相撲」や「日本で活躍する力士たち」のイメージが強かったのと、モンゴルから札幌山の手高校へ留学し、現在は国士舘大学でラグビーを続けている選手の話も耳にしていたので、モンゴルラグビーにも興味を抱いていた。しかし、それ以外の文化や社会についてはあまり知らなかったため、今回の訪問はまさに未知の場所に足を踏み入れる体験であり、ワクワクしていた。

首都ウランバートルで見聞きしたこと
ウランバートルは、旧ソ連の影響を強く受けた名残を今も感じる一方で、人々の間には前向きに未来を切り開こうとする空気も漂っていた。そして、街の人々はとても親切で、バスの運転手やガイドの方々からも温かな思いやりを感じた。治安もよく、朝のランニングも安心して楽しめるほどだった。(雨が降ると至るところに水たまりができてしまって、インフラ整備はこれからかな)
一方で、資源を中国に輸出してから再輸入するという非効率な構造や、ロシアと中国に挟まれたエリアでもあり、経済発展の難しさも垣間見えた。40年前までソ連だった影響もあり、ロシア語での記載が多く、おじいちゃんおばあちゃんはロシア語を流暢に話す。内モンゴルに残っているモンゴル文字は、日本語のような縦書きだが、ウランバートルでは横書きであった。縦書きの文字は読めない人も増えているようだ。
ウランバートルは冬がとてつもなく寒く、マイナス30度にまで達する。そのため、街のインフラとして火力発電が整備されており、そこで発電したエネルギーを用いて、各家庭にお湯や熱量が分配される仕組みとなっている。暖房をつけない状態で家に帰っても、温かい部屋になっているらしい。ウランバートルならではのインフラがある。(火力発電の大きなプラントの一つが壊れたので、今年の冬は大変かもしれないらしい) 冷涼な気候を生かしたデータセンターなど、新しいビジネスの可能性もあるかもしれない(依文さんが教えてくれた)

海外に行くと必ずスーパーを訪問する。スーパーではロシア産の炭酸水や韓国の食材が目立ち、食文化の多様さも垣間見えた。ロシアの温泉地域から抽出される炭酸水はミネラルが豊富でとても美味しかった。(ローカル情報によると二日酔いにめちゃ効くらしい 笑) 一方で、中国・インド料理は少ない印象を受けた。また、食事の量はとにかく多いが、人々の体型は引き締まっており、不思議な印象を受けた。自然との触れ合いが残る中で、質素なシンプルな生活を好むのかもしれない。また。炭水化物を多く摂るというよりはお肉中心の生活の影響があるのかもしれない。

大草原・国立公園で体験したこと
都会・ウランバートルを離れると、一面に広がる草原と雄大な自然が待っていた。
ハイライトのひとつ、乗馬体験ではただ馬に乗るだけではなく、スピードを上げて風を切る感覚や、羊の群れを誘導する牧畜の一端に触れることができた。道なき道を進む感覚は、まるで映画の世界に飛び込んだかのようで、日本ではなかなか味わえないスリルと自由を堪能した。

ゲルでの食事も印象的だった。塩気を基調としたシンプルな味わいだが、持参した生しょうゆ糀やにんにく・しょうが生塩糀を合わせることで、味に少し変化が生まれた。羊の解体を見学した経験は少し残酷ではあったが、命をいただく重みを実感し、その後の食事がよりありがたいものに感じられた。これまで食べた羊の中で一番美味しかったのは、味だけでなく、その過程を目の当たりにしたからだと思う。また、食事の後に温かいものを飲んで、歯についた脂を流すことや、胃の中を温めるのも理にかなっている。場合によっては、ウォッカを少し飲むこともあるようだ。(やってみれば良かったか!)

そして何よりも感動したのは、国立公園で見た幻の野生馬「タヒ」だ。一度は絶滅の危機に瀕したこの馬が群れを成して歩く姿は、まさに大自然の奇跡のようで、静謐さと力強さを兼ね備えた光景だった。人間が脇役となり、自然と動物が主役になる場所に立つと、地球の中で自分がどれだけ小さな存在であるかを思い知らされる。

旅を特別なものにしてくれた同行メンバーたち
まず、この旅を実現できたのは、友人の平原依文さんのおかげだ。「OeGG」とのご縁も彼女からの紹介がきっかけで、モンゴル行きを決めた打合せにも同席していて「ぜひ、いきましょう!」と言ってくれた。挑戦を惜しまないエネルギッシュな方で、宮崎での田植えイベントにもさっと駆けつけてくれるような行動力がある。モンゴル滞在中も人との関わり方や場を和ませる配慮に感銘を受けた。彼女が掲げる「境界を溶かす」というミッションを自然と体現している姿も素敵だった。彼女のことを詳しく知らなければ、女性起業家で強そうなイメージがあるかもしれない。僕もそんなイメージが頭の片隅にありつつ、一緒に旅に出たのだが、とてもしなやかで和やかな方だった。羊の解体には近づけなくて、動物への愛や繊細さも持ち合わせており、親近感が湧いた。
同行していただいた若いスタッフの方たちのパワーと旅を通して成長する姿もとても居心地が良かった。やったことないMCをやりきることや、「羊の解体は絶対に無理!!」と言っていたのに、気がついたら隣でビデオ撮影をしていて、食べ物への感謝を述べたりしている姿は、日本の若い世代の可能性を大いに感じた。日本を飛び出し、さまざまな体験をする。我々はもっとそういった場を用意しないといけないなと思った。
ツアーを通して出会ったコーディネーター兼通訳のズラさんも忘れられない。モンゴルを深く愛し、日本や世界の歴史にも通じていて、経済や地政学、若者の考え方など多くを教えてくれた。
そして現地で出会った、たくさんのモンゴルの方達。モンゴルでは、家族を大切にし、年長者を敬う文化を持っている。その姿勢に触れる中で、自分自身も改めて「家族や年上の人をもっと大切にする」という当たり前の価値観を見直すきっかけを得た。

今回の旅は、モンゴルの文化や歴史、自然を通して、日本の若者との触れ合いを通して、自分の生き方を問い直す大きな学びとなった。携帯電話をほとんど見ずに過ごした数日間は、自然や仲間、人との対話に没頭する豊かな時間となった。
FIN――
・企業、団体の組織力向上やリーダーの育成を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・スポーツの価値向上を目的とした講演およびイベント出演のご依頼
・メディア出演のご依頼
について、お気軽にこちらのフォームよりお問い合わせください。
追ってこちらからお返事させていただきます。

